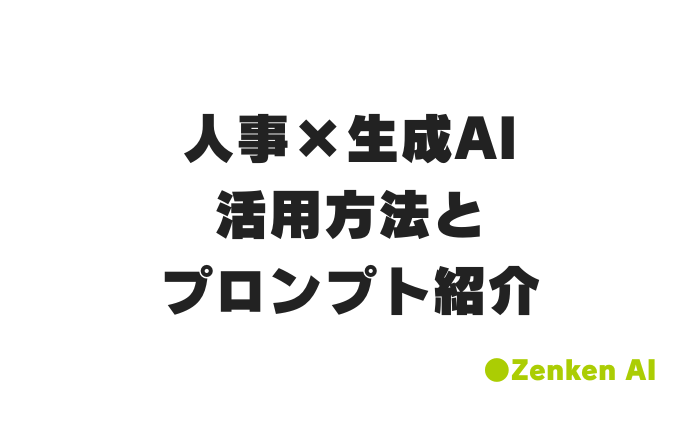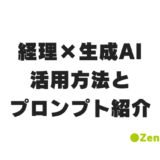近年、生成AIの活用により、求人票作成、履歴書の整理、評価コメントの下書き、研修資料の準備といった定型業務を大幅に効率化できるようになりました。これにより生まれた時間を、従業員との面談やキャリア支援、人材戦略の立案といった、より価値の高い業務に集中することが可能になります。
本記事では、人事業務における生成AIの活用方法をご紹介します。
海外動向と示唆:人事の仕事は「置き換え」ではなく「再定義」へ
まず海外の動向を見てみましょう。
海外では、生成AI技術の導入とともに、特にバックオフィス業務において職務内容の変化が起きているニュースがあります。例えば、IBMは人事部門にAIエージェントを導入し、従来人間が行っていた採用プロセスの一部を自動化する取り組みを進めるニュースもありました。また、一部の企業では「AIで自動化できない職種を優先的に採用する」という方針を公表するなど、業務の再編成が始まっています。
しかし、国際労働機関(ILO)の分析によると、多くの仕事がAIに完全に代替されるのではなく、「職務の再定義」が起こっているという点です。つまり、単純な事務作業がAIによって自動化される一方で、人間はより戦略的な人事施策の立案や、従業員との深いコミュニケーションなど、人間ならではの価値を発揮する業務に集中できるようになってきているのです。
これは人事業務においても同様で、定型的なタスクの自動化により、人事担当者がより本質的で創造的な業務に時間を割けるという、仕事の「質の変化」が世界的に進行していることを意味しています。
参照リンク
国際労働機関(ILO)、生成AIが雇用に与える潜在的影響をグローバル分析
IBM CEO、バックオフィス職の30%は5年でAIが代替と予想 – Bloomberg
人事の役割変化:定型作業の半自動化で「人材戦略」に時間を振り向ける
人事業務の多くを占める求人票作成、履歴書整理、評価コメント作成、研修資料作成などの定型的なタスクは、まさに生成AIが最も力を発揮する領域です。これらの作業をAIに任せることで、人事担当者は時間的・精神的な余裕を手に入れることができます。
その結果、これまで忙しさに追われてできなかった「なぜこの優秀な人材が離職したのか」という深掘り分析や、「どうすれば従業員のエンゲージメントをより高められるか」といった戦略的な施策立案に集中できるようになります。
例えば、キャリア面談においては、AI分析を活用することで従業員一人ひとりの経歴や志向をより深く理解し、個別最適化されたサポートを提供できるようになります。面談前の情報整理にかかっていた時間を、実際の対話や関係構築により多く割けるのです。
これは、人事担当者が単なる「事務処理に追われる状態」から、企業の人材戦略を支える「人材戦略家」や「従業員体験の設計者」へと進化する機会を意味します。定型業務から解放されることで、人間だからこそ発揮できる洞察力や共感力、創造性といった価値を、より高いレベルで活用できるようになるのです。
AIツールを使うときに守るべきセキュリティ
個人情報や機密情報を扱う人事だからこそ、AIを安全に使えるように次の内容を把握しておきましょう。最低限、学習機能のオフ設定は必須です。
学習オフを徹底する
なにも設定せずにAIを利用した場合、入力した内容がAIの学習データとして使われ、他の人への回答に含まれてしまう可能性があります。
例えば、「田中太郎さんの今回の評価はB+で、営業成績は良いのですが協調性に課題があります…」と入力したとします。数日後、どこかの誰かが「営業職の評価事例を教えて」とAIに質問したら、あなたが入力した内容が回答例として表示されてしまうかもしれません。
そのため、ChatGPT、Claude、Geminiなど、どのAIツールを使う場合も、まず最初に「学習機能をオフ」に設定することが必須です。各サービスの設定画面で「データを学習に使用しない」といった項目を探して、必ずオフにしてください。
会社のAIガイドラインを事前確認
学習オフに設定しても、入力データは一時的にサーバーに保存されることがあります。「どこまでの情報なら入力してもいいのか?」—これは会社によって基準が異なります。AIツールの利用を完全に禁止している企業もあれば、一般的な業務相談程度なら問題ないという企業もあります。
AIツールを使い始める前に、上司や情報システム部門に「AIツールの利用について、会社のルールはありますか?」と確認しましょう。
機密情報の取り扱いに注意する
従業員の氏名・住所・給与・評価情報、採用候補者の個人情報、人事制度の詳細内容、組織改編や人事異動の計画、労働条件や契約内容など、会社や個人の機密に関わる情報の入力には十分注意が必要です。
代わりに「一般的な事例」や「仮想的な状況」として質問することで、機密情報を守りながらAIの知恵を借りることができます。「Aさんという営業職の方が…」ではなく「営業職の従業員が協調性に課題がある場合の指導方法は?」といった形で相談しましょう。
AIツール別の設定方法
ChatGPT – 設定内のデータコントロールからオフ
学習オフの設定方法
- ChatGPTにログイン後、右上、または左下のアイコンをクリック
- 「設定」を選択
- 「データコントロール」をクリック
- 「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにする
管理モードなどのあるChatGPT TeamプランやEnterpriseプランでは、最初から学習機能がオフになっているので、個別設定は不要です。
Claudeのデータ利用仕様(学習/フィードバック)
Claudeはデフォルトで学習機能がオフになっています。つまり、特別な設定をしなくても、入力した内容が学習に使われることはありません。
注意点 フィードバック、アイデア、改善案などの提案を送信することによって、明示的な許可を与えた場合に限り、モデルのトレーニングに使用されることがあるため、機密情報を扱う際は、フィードバックボタンは押さないようにしましょう。
Google Gemini – Google Workspace環境推奨
企業利用が前提
Google Geminiを使用する際は、Google Workspaceの法人契約と一緒に使うことをおすすめします。
個人アカウントでの問題点
個人のGoogleアカウントでGeminiを使う場合、学習オフ設定(アクティビティをオフ)にすると、チャット履歴が保存されないため、少し使いづらくなってしまいます。
Google Workspace利用企業には最適
既にGoogle Workspaceを導入している企業なら、2025年1月からBusinessプランとEnterpriseプランにGeminiが標準搭載されているため利用できます。
注意事項:ログデータは一定期間保管される
学習に使われなくても、入力したデータは不正利用チェックや法的対応のため、一定期間サーバーに保管されます。これは各社が行っている一般的な措置です:
- ChatGPT:学習オフ設定後も30日間はデータが保管される。プランによってその限りではない
- Claude:30日以内にバックエンドで自動削除
- Gemini:アクティビティ設定で3か月〜36か月から選択可能
つまり、 学習には使われないものの、データ自体は各社のサーバーに一時保管されており、この期間中は技術的にはアクセス可能な状態にあります。そのため、企業として許容できる情報レベルを事前に決めておく必要があります。
実際の運用では社内ルールで「どこまでOK」かを明確にしておくことが重要です。
この保管期間を理解した上で、自社の情報管理方針と照らし合わせて利用範囲を決めることが大切です。完全にデータが残らない状態ではないことを前提に、業務効率化とのバランスを取って活用しましょう。
すぐに使える人事業務のプロンプト例
ここからは、今日から実際に試せる具体的な活用例をご紹介します。段階的に導入することで、無理なくAIスキルを身につけることができます。
文書作成のAI活用(求人票・評価コメント・研修資料)
人事業務の大部分を占める文書作成作業は、生成AIによって効率化できます。従来は白紙から文章を考える必要があったタスクも、AIを使えば質の高い下書きを数分で作成し、それをベースに自社に合わせてカスタマイズするだけで完成します。
求人票作成の効率化
求人票作成は、従来であれば条件整理から文章作成まで時間がかかる業務です。しかし、AIを活用すれば10分程度で魅力的な下書きが完成します。
プロンプト例:
ITエンジニア、正社員、東京勤務、年収400-600万円、リモートワーク可、の条件で魅力的な求人票を作成してください。応募者が興味を持ちやすい表現を心がけてください
AIが生成する文章は、職務内容の魅力的な表現、求める人物像の明確化、働き方の特徴などを含んだ構成になります。これをベースに、自社の具体的なプロジェクト名、使用技術、チーム体制などの詳細を追加するだけで、応募者にとって魅力的な求人票が完成します。
評価コメント作成の支援
評価コメントは、建設的でありながら改善点も明確に伝える必要がある業務の一つです。AIは、ポジティブな表現を保ちながら改善すべき点を適切に指摘する文章を提案してくれます。
プロンプト例:
営業成績は目標を達成しているが、報告書の提出が遅れがちな部下への評価コメントを、改善点を指摘しつつも前向きな表現で作成してください
生成されたコメントでは、まず成果を認める表現から始まり、改善点を「成長機会」として捉える前向きな表現で構成されます。これにより、評価対象者のモチベーションを下げることなく、具体的な改善行動を促すことができます。
研修資料作成の高速化
新人研修やスキルアップ研修の資料作成も大幅に効率化されます。テーマと対象者、時間を指定するだけで、学習目標から具体的な内容まで体系的な研修プログラムが提案されます。
プロンプト例:
新入社員向けのビジネスマナー研修資料を作成してください。挨拶、メール、電話応対、服装について、各30分程度で説明できる内容でお願いします
従来は参考書を調べながら数日かけて作成していた研修資料も、AIの提案をベースに自社の文化や具体例を追加するだけで、完成させることができます。
人事データの分析支援(履歴書要約・面接評価整理・アンケート分類)
人事業務では膨大な情報を整理・分析する作業が頻繁にあるかと思います。履歴書の山、面接メモ、アンケート回答など、これらの情報処理にAIを活用することで、分析時間を大幅に短縮できます。
履歴書・職務経歴書の要約
中途採用の選考では、数十件から数百件の応募書類を確認する必要があります。従来は一件ずつ読み込んで手作業でまとめていた作業も、AIを使えば瞬時に要点を抽出できます。
履歴書の内容をテキスト化してAIに入力し、以下のように依頼します:
この候補者の強みと経験を3点で要約してください
AIは職歴、スキル、実績を整理し、「5年間のWebマーケティング経験」「Google Analytics認定資格保有」「前職でCV率を20%改善した実績」といった形で、採用判断に必要な情報を簡潔にまとめてくれます。100件の応募があった場合、従来なら数日かかっていた初期スクリーニングを短時間で完了できます。
面接結果の整理
複数の面接官が参加する選考では、それぞれの評価コメントを統合して総合判断を行う必要があります。AIを活用すれば、各面接官の主観的なコメントを客観的に整理できます。
この候補者への評価をポジティブ要素とネガティブ要素に分けて整理してください
「技術力は高い」「コミュニケーション能力に不安」「リーダーシップ経験が豊富」といった散らばったコメントを、「強み:技術力・リーダーシップ」「懸念点:コミュニケーション」として整理し、採用会議での議論を効率化できます。
従業員アンケート分析
年次の満足度調査や職場改善アンケートでは、数百件の自由記述回答を分析する必要があります。従来は手作業で分類していた作業も、AIを使うことで最初の整理ができます。
プロンプト例:
以下のアンケート回答を、『職場環境』『人間関係』『業務内容』『待遇』の4つのカテゴリに分類して要約してください
「残業が多すぎる」「上司との関係が良好」「新しいスキルを身につけられる」「給与に満足」といった様々なコメントが、カテゴリ別に整理され、改善すべき優先順位も明確になります。
キャリア支援の高度化(面談準備・個別アドバイス・フォローアップ)
AIの活用により、従業員一人ひとりにより個別最適化されたキャリア支援を提供できるようになります。限られた面談時間をより効果的に使い、継続的なフォローアップも充実させることが可能です。
面談前準備の自動化
効果的なキャリア面談を行うためには、事前準備が重要です。AIを活用すれば、従業員の状況に応じた質問項目や確認事項を効率的に準備できます。
営業職3年目、昇進意欲が高い従業員との面談で確認すべきポイントを5つ教えてください
AIは「現在の業務で感じている課題」「管理職に求められるスキルの習得状況」「具体的なキャリア目標とタイムライン」といった、その従業員の状況に特化した質問リストを提案します。これにより、面談時間を最大限活用し、従業員にとって価値のある時間にできます。
個別アドバイス生成
従業員の経歴、希望、会社の方針を考慮した個別のキャリアアドバイスも、AIの支援により質の高い提案ができます。
マーケティング経験3年、MBA取得希望、管理職志向のある従業員に対する今後2年間のキャリア開発プランを提案してください
AIは「1年目:プロジェクトリーダー経験の積み重ね」「1年半後:MBA取得開始」「2年目:部門マネージャー候補として育成」といった具体的なステップを提案します。これをベースに、社内の実際のポジションや研修制度と照らし合わせることで、実現可能性の高いキャリアプランを作成できます。
フォローアップ計画作成
キャリア面談後の継続的なサポートも、AIを活用して体系的に計画できます。
この従業員に対する3か月後、6か月後の確認事項と支援策を提案してください
面談内容を整理した後、「3か月後:新プロジェクトでの進捗確認」「6か月後:スキル習得状況の評価と次のステップ検討」といった具体的なフォローアップ計画が立案されます。これにより、従業員のキャリア開発を継続的にサポートできます。
戦略人事の検討支援(制度設計・他社リサーチ)
定型業務の効率化により創出された時間は、人事の本質的価値である戦略立案や制度設計に活用できます。AIは、これらの高度な業務においても強力な思考パートナーとして機能します。
人事制度設計の支援
組織の課題に対する人事制度の改善は、多角的な検討が必要な複雑な業務です。AIを活用すれば、様々な選択肢を体系的に検討できます。
離職率が高い営業部門の人事制度改善策を、評価制度、報酬制度、キャリアパスの観点から提案してください
AIは「成果主義的な評価制度の見直し」「インセンティブ設計の改善」「管理職への昇進パスの明確化」といった多面的な改善案を提案します。これらの提案をベースに、自社の状況や予算制約を考慮した実現可能な施策を選択し、具体的な実行計画を立てることができます。
競合他社調査の効率化
業界のベストプラクティス調査や他社事例の収集も、AIを活用すれば効率的に実施できます。
IT業界の中小企業における一般的な評価制度の特徴と、従業員満足度向上のための工夫を教えてください
AIは業界トレンドや一般的な制度設計について包括的な情報を提供します。従来なら数日かけて調査していた内容も、短時間で整理できるため、より多くの時間を自社に適した施策の検討に充てることができます。
これらの活用により、人事担当者は単純作業から解放され、従業員一人ひとりへの支援品質向上と、組織全体の人材戦略により多くの時間を投資できるようになります。
AI時代の人事プロフェッショナルとして未来を切り拓く
生成AIは人事業務に革命的な変化をもたらし、仕事の質を大幅に向上させる機会を提供しています。
これまで人事担当者の時間の大部分を占めていた求人票作成、履歴書整理、評価コメント作成といった定型業務がAIによって効率化されることで、従業員一人ひとりとの深い対話、組織全体のエンゲージメント向上施策の立案、データに基づいた人材戦略の構築といった、より価値の高い業務に集中できるようになります。
AI時代の人事担当者には、AIが提供する情報を適切に解釈し活用する能力と、安全にツールを使いこなすデジタルリテラシーが求められます。同時に、AIがどれほど発達しても、「人と人との関係構築」「個々人の成長支援」「組織文化の醸成」といった人事の核心的価値は、人間だからこそ発揮できる領域であり続けます。
まずは本記事で紹介した基本的な活用方法から始めて、継続的に新しいスキルを習得していくことが重要です。生成AIの登場は、人事担当者が自分自身の価値と可能性を再発見する絶好の機会です。「AIで仕事を進化させる」という成長マインドセットで、新しい時代の人事プロフェッショナルとしての道を切り拓いていきましょう。