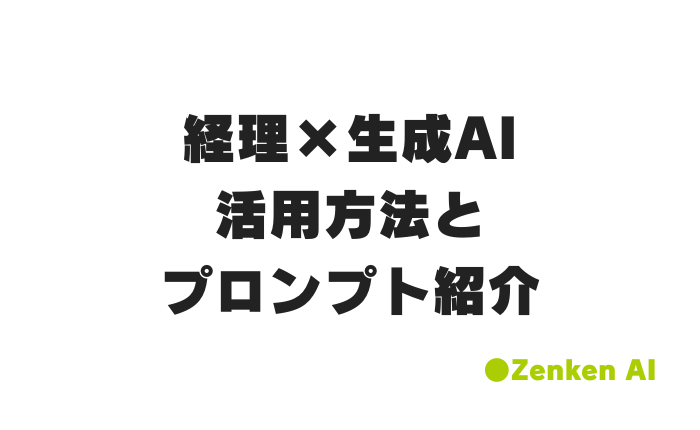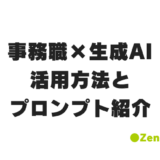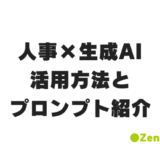生成AIを活用し、文書作成、財務分析、資料骨子の作成といった業務を大幅に効率化できるようになりました。これにより生まれた時間を、財務分析、経営への提言、戦略的な業務改善といった、より価値の高い業務に集中することが可能になります。
数字と向き合い、正確性を何より重視する経理業務をされている方々にとって、AIは業務品質を向上させる強力なパートナーとなります。本記事では、経理業務におけるAIの活用方法から具体的なプロンプト例までご紹介します。
経理の役割は“入力中心→提案型”へ進化する
実際のところ、海外のニュースでは既にAI導入による変化が始まっていることがわかります。例えば、IBM社では「人事や総務などのバックオフィス業務の約30%が、5年以内にAIに置き換わる可能性がある」と発表しました。具体的には、書類作成や人事異動の手続きなど、いわゆる「定型業務」から変わっていくとのこと。
実は、AIが仕事を進化させます。
国際労働機関(ILO)の分析によると、AIは仕事を「奪う」より「補強する」影響の方が大きいと分析されています。つまり、完全に人がいらなくなるのではなく、仕事の内容が変わっていくということです。
経理における役割進化のイメージ
| Before(従来) | After(AI時代) |
|---|---|
| データ入力・計算・書類作成に1日の大半を使わざるをえないことも | 繰り返し・定型作業はAIに任せ、数字の分析や経営への提案に時間を使える |
| 「計算」「繰り返し作業」 | 「数字を読み解き価値を生み出す」 |
参照リンク
国際労働機関(ILO)、生成AIが雇用に与える潜在的影響をグローバル分析
IBM CEO、バックオフィス職の30%は5年でAIが代替と予想 – Bloomberg
AIを”アシスタント”に変えるマインドセット
「AIはどういう存在か」—この質問への答えは実はシンプルです。AIは、あなたが今まで欲しかった”理想のアシスタント”そのものなんです。
AIが持つ理想的なアシスタントの立ち位置
想像してみてください。24時間いつでも働いてくれて、何度でもやり直してくれる。計算の補助もしてくれて、「これ、どう書いたらいいですか?」と聞けば即座にアイデアをくれる。—そんなあなた専任のアシスタントがいたら、どれだけ業務が楽になるでしょうか。
AIはまさにこうした特徴を備えています。経理業務で頭を悩ませる繰り返し作業や、文書作成の下書き、データ分析のたたき台作成など、これまで時間のかかっていた業務を瞬時にサポートしてくれます。
AI導入で経理の1日はこう変わる
従来は請求書データの手入力作業、経費精算の確認・修正、月次報告書の作成など、1日の大半が定型業務に占められているかもしれません。しかしAI活用後は、これらの作業時間が大幅に短縮されます。
例えば、AIに「提供する今月の経費で〇〇のような異常値はありますか?」と質問すれば回答を得られ、「取引先への催促文を丁寧なトーンで作成してください」と依頼すれば下書きが完成します。「売上データから注意すべきポイントを3つ教えてください」と尋ねれば、分析のたたき台も用意されます。
その結果、生まれた余白の時間を丸々、経営陣への提案資料作成や財務戦略の検討といった、より価値の高い業務に集中できるようになるのです。
AIとの理想的な役割分担
AIを「パートナー」として捉える視点が重要です。AIには面倒な作業、計算、下書き、アイデアの提案を任せる一方、最終判断、責任、クリエイティブな思考、人とのコミュニケーションは経理のプロであるあなたが担います。
例えば、AIに「予算と実績の差異分析をしてください」とお願いすれば、数秒で分析結果をまとめてくれます。しかし「この差異は許容範囲なのか?」「どのような対策を講じるべきか?」という経営判断は、やはり経理のプロフェッショナルにしかできません。
AIツールを使うときに守るべきセキュリティ
機密情報を扱う経理だからこそ、AIを安全に使えるように次の内容を把握しておきましょう。「便利だから」といって何でも入力してしまうのは非常に危険です。
学習オフを徹底する
なにも設定せずにAIを利用した場合、入力した内容がAIの学習データとして使われ、他の人への回答に含まれてしまう可能性があります。
例えば、「弊社の売上は3億円で、利益率が15%なのですが…」と入力したとします。この入力内容をAIが学習した場合、どこかの誰かが「中小企業の経理事例を教えて」とAIに質問したら、あなたが入力した内容が回答例として表示されてしまうかもしれません。
そのため、どのAIツールを使う場合も、まず最初に「学習機能をオフ」に設定することが必須です。各サービスの設定画面で「データを学習に使用しない」といった項目を探して、必ずオフにしてください。
会社のAIガイドラインを事前確認
「どこまでの情報なら入力してもいいのか?」—これは会社によって基準が異なります。
AIツールを使い始める前に、上司や担当部門に「AIツールの利用について、会社のルールはありますか?」と確認しましょう。
機密情報の取り扱いに注意する
売上高、利益、予算などの具体的な数値、取引先名、顧客名、銀行名、社員の給与や個人情報、契約内容や機密事項など、会社の機密に関わる情報の入力には十分注意が必要です。
代わりに「一般的な事例」や「仮想的な状況」として質問することで、機密情報を守りながらAIの知恵を借りることができます。
AIツール別の設定方法
ChatGPT – 設定内のデータコントロールからオフ
学習オフの設定方法
- ChatGPTにログイン後、右上、または左下のアイコンをクリック
- 「設定」を選択
- 「データコントロール」をクリック
- 「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにする
管理モードなどのあるChatGPT TeamプランやEnterpriseプランでは、最初から学習機能がオフになっているので、個別設定は不要です。
Claudeのデータ利用仕様(学習/フィードバック)
Claudeはデフォルトで学習機能がオフになっています。つまり、特別な設定をしなくても、入力した内容が学習に使われることはありません。
注意点 フィードバック、アイデア、改善案などの提案を送信することによって、明示的な許可を与えた場合に限り、モデルのトレーニングに使用されることがあるため、機密情報を扱う際は、フィードバックボタンは押さないようにしましょう。
Google Gemini – Google Workspace環境推奨
企業利用が前提
Google Geminiを使用する際は、Google Workspaceの法人契約と一緒に使うことをおすすめします。
個人アカウントでの問題点
個人のGoogleアカウントでGeminiを使う場合、学習オフ設定(アクティビティをオフ)にすると、チャット履歴が保存されないため、少し使いづらくなってしまいます。
Google Workspace利用企業には最適
既にGoogle Workspaceを導入している企業なら、2025年1月からBusinessプランとEnterpriseプランにGeminiが標準搭載されているため利用できます。
注意事項:ログデータは一定期間保管される
学習に使われなくても、入力したデータは不正利用チェックや法的対応のため、一定期間サーバーに保管されます。これは各社が行っている一般的な措置です:
- ChatGPT:学習オフ設定後も30日間はデータが保管される。プランによってその限りではない
- Claude:30日以内にバックエンドで自動削除
- Gemini:管理者が3か月〜36か月から選択可能
つまり、 学習には使われないものの、データ自体は各社のサーバーに一時保管されており、この期間中は技術的にはアクセス可能な状態にあります。そのため、企業として許容できる情報レベルを事前に決めておく必要があります。
実際の運用では社内ルールで「どこまでOK」かを明確にしておくことが重要です。
この保管期間を理解した上で、自社の情報管理方針と照らし合わせて利用範囲を決めることが大切です。完全にデータが残らない状態ではないことを前提に、業務効率化とのバランスを取って活用しましょう。
検証プロセス:AI回答を必ず裏取りするTips
AIは確かに便利ですが、完璧ではありません。経理という正確性が命の仕事だからこそ、AIとの正しい付き合い方を身につけましょう。
AIの仕組みを理解しておこう
AIは「確率的に最も適切と思われる答え」を生成するツールです。つまり、人間のように「正確な知識」「背景情報」をすべて持っているわけではなく、大量のデータから「こういう質問にはこう答えるのが一般的だろう」という推測で回答しています。
そのため、時として存在しない法令を堂々と説明したり、架空の事例を実在するもののように語ったりすることがあります。この現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、どんなに優秀なAIでも完全には避けられない問題です。
特に慎重になるべき分野
経理業務の中でも、以下の分野についてはAIの回答をそのまま信用するのは危険です:
税務処理や会計基準の解釈では、法改正や最新の通達が反映されていない可能性があります。また、法的判断を伴う事項については、AIの回答はあくまで一般論であり、あなたの会社の具体的な状況には当てはまらないかもしれません。
これらの分野では、AIの回答を参考程度に留めて、必ず税理士や弁護士などの専門家、または最新の公式資料や社内資料で確認することが重要です。
AIを「たたき台作成者」として活用する
では、AIをどう活用すればいいのでしょうか。答えは「たたき台の作成者」として使うことです。
例えば、月次報告書を作成する際、「今月の売上分析で注意すべきポイントを教えてください」とAIに質問すれば、分析の視点やアプローチのアイデアを提案してくれます。ただし、そのアイデアが実際のデータと照らし合わせて適切かどうか、最終的な判断は必ずあなたが行います。
文書作成でも同様です。「経費精算の却下理由を丁寧に説明する文章を作成してください」と依頼すれば下書きを作ってくれますが、会社の方針や具体的な状況に合わせて修正するのは人間の役割です。
AIと人間の理想的な分担
AIには「アイデアの提案」「下書きの作成」「分析の視点提示」を任せ、人間は「最終判断」「責任」「品質管理」を担う—この分担を意識することで、AIを安全かつ効果的に活用できます。
AIは優秀なアシスタントですが、経理の最終責任者はあくまであなた自身です。この原則を忘れずに、AIと上手に付き合っていきましょう。
経理向け文書作成プロンプト集
「文章を書くのが苦手…」「毎回同じような文書で時間がかかる…」そんな悩みを抱えている経理担当者は多いのではないでしょうか。実は、文書作成こそAIが最も得意とする分野の一つです。
経費精算でよくある「却下理由」の作成
経費申請を却下する際の説明文書は、相手を不快にさせず、でも規程はしっかり伝える微妙なバランスが求められます。そんな文章をAIに任せてみましょう。
プロンプト例:
経費精算で新幹線のグリーン車料金が申請されましたが、社内規程では普通車のみが承認対象です。申請者に対して丁寧かつ分かりやすく説明する文書を作成してください。今後の関係も考慮した適切なトーンでお願いします。
AIは提供した情報をもとに、相手の立場を配慮しながらも規程をしっかりと伝える文章を提案してくれます。あとは、あなたの会社の文体や方針に合わせて微調整するだけです。
売掛金の催促文書で頭を悩まさない
取引先への催促状は、厳しすぎて関係を悪化させたくないし、でも甘すぎても回収が進まないというジレンマがあります。そんな課題への悩みもAIが解決してくれます。
プロンプト例:
3か月間延滞している取引先への売掛金催促状を作成してください。今後の取引継続も考慮し、厳しすぎず甘すぎない、プロフェッショナルなトーンで書いてください。支払いスケジュールの相談も受け入れる姿勢を示してください。
財務諸表注記の下書きも瞬時に
決算時期の財務諸表注記は、専門的で分かりにくい内容をステークホルダーに理解してもらえる文章にする必要があります。理解しやすいように情報粒度の変更や表現方法はAIにお願いしてみましょう。
プロンプト例:
当期に発生した設備の減損損失について、株主や銀行などのステークホルダーに分かりやすく説明する注記文を作成してください。専門用語を使いすぎず、背景と今後の見通しも含めて説明してください。
監査対応資料の構成で迷わない
監査法人への説明資料作成では、どんな構成にすれば分かりやすく伝わるかが重要になります。AIに構成案を作ってもらいましょう。
プロンプト例:
内部統制の軽微な不備について監査法人に説明する資料を作成したいです。問題の概要、原因分析、改善策、今後の予防策を含む資料の構成案を提案してください。監査法人が知りたいポイントを重視してください。
効果的なプロンプトを作る3つのコツ
AIに質問する際は、以下の要素を含めると、より精度の高い回答が得られます。
状況説明をしっかりと行い、読み手は誰かを明確にし、求めるトーンや文体を指定する—この3点を意識するだけで、AIの回答品質が格段に向上します。
例:
経理担当者として、○○について△△の目的で文書を作成したい。読み手は××で、トーンは□□でお願いします
必ず覚えておきたい注意点
AIが生成した文章は、必ず内容を確認し、あなたの会社の方針や正確な事実に基づいて修正してください。AIは素晴らしい下書きを作ってくれますが、最終的な内容の責任はあなたにあります。
また、相手方の名前や具体的な金額など、機密情報を含む場合は、AIで下書きを作った後に手動で追加するようにしましょう。
文書作成でのAI活用は、慣れてしまえば手放せないツールになります。最初は簡単な文書から始めて、徐々に活用範囲を広げていってください。
財務分析AIプロンプト集
数字は読めるけど「なぜこうなったのか?」「どこに注意すべきか?」の分析に時間がかかる—そんな悩みを抱える経理担当の方もいるかもしれません。AIを分析パートナーとして活用すれば、データの裏にある「気づき」を効率よく発見できます。
予算と実績の差異分析でAIを活用
例えば、月次の予算実績管理で、単に「売上が予算より20%下回った」という事実は分かっても、その要因分析に頭を悩ませることがあるかもしれません。そんな時こそAIの出番です。
プロンプト例:
売上が予算より20%下回っている状況です。考えられる要因を以下の3つの観点で分析してください:
1. 業界全体のトレンド要因
2. 季節・時期的要因
3. 社内の営業・マーケティング要因
それぞれについて、確認すべきデータや改善のヒントも含めて提案してください。
AIは様々な角度からの分析視点を提示してくれるので、あとはあなたの会社の実情と照らし合わせて、最も可能性の高い要因から調査していくことで客観的な視点を踏まえた分析を進めることができます。
財務比率の異常値を見つける方法
財務分析で「この数値、同業他社と比べてどうなんだろう?」と疑問に思うことがあるかもしれません。AIに業界平均との比較分析を依頼してみましょう。
プロンプト例:
当社の流動比率が1.2で、同業他社平均が1.8です。この差が生まれる原因として考えられる要因と、財務担当者として確認すべきポイント、改善策があれば教えてください。
AIは一般的な原因候補を整理してくれるので、実際の項目と突き合わせて検証していけば、効率的に問題点を特定できます。
投資判断で見落としがちなリスク
設備投資や新システム導入の検討時、財務面でのリスク評価は重要ですが、見落としがちなポイントもあります。抜け漏れがないようにAIにチェックリストを作ってもらいましょう。
プロンプト例:
新システム導入(投資額5000万円)を検討中です。財務担当者として検討すべきリスクと評価ポイントを、以下の観点で整理してください:
- キャッシュフロー への影響
- 減価償却・税務上の取り扱い
- ROI・回収期間の妥当性
- 導入失敗時のリスク
異常値を発見した時の原因分析
定例の数値チェックで異常値を発見した時、「何から調べればいいか分からない」という状況があるかもしれません。AIに調査の道筋を作ってもらいましょう。
プロンプト例:
前月比で売上原価率が5%上昇しています。この変化の原因として考えられる要因と、確認すべきデータ・資料を優先順位をつけて教えてください。緊急度が高いものから順番に提示してください。
AIを分析パートナーにするコツ
AIに分析を依頼する際は、具体的な数値や状況を説明し、「仮説立案」「確認すべきポイント」の提案を求めることが重要です。ただし、業界の特殊性や会社固有の事情は、あなた自身が補完する必要があります。
また、AIの提案はあくまで「分析の入り口」として活用し、最終的な判断は必ず経理のプロフェッショナルであるあなたが行ってください。AIが提示した仮説を、実際のデータと会社の状況で検証し、本当の原因を突き止めることで、経営陣により価値の高いインサイトを提供できるようになります。
AIを使えば、従来なら数時間かかっていた分析の方向性検討が数分で完了します。浮いた時間を使って、より深い分析や改善提案に集中していきましょう。
経営報告を効率化するAIプロンプト集
「数字は整理できたけど、どう伝えれば経営陣に響くんだろう?」「プレゼン資料の構成で毎回悩む…」そんな経験はありませんか。AIを活用すれば、説得力のある報告資料を効率的に作成できます。
月次報告で経営陣の関心を引く要約作成
毎月の財務報告で、膨大なデータの中から「経営陣が本当に知りたいこと」を抽出するのは時間がかかるかもしれません。まずはAIに要約のポイントを整理してもらいましょう。
プロンプト例:
今月の売上は前年同月比8%減、営業利益は15%減、現金残高は前月比200万円増となりました。この数値から経営陣が知るべき重要ポイント3つと、来月注意すべき点を要約してください。経営判断に必要な視点を重視してください。
AIは数値の背景にある意味や、経営陣が気にすべき点を整理してくれます。それをベースに、あなたの会社の実情に合わせて調整すれば、的確な月次報告が完成します。
取締役会資料の構成立案
四半期決算の取締役会資料は、限られた時間で要点を伝える必要があります。効果的な構成をAIに提案してもらいましょう。
プロンプト例:
四半期決算について取締役会で報告する資料を作成します。以下の情報を含む効果的な構成案を提案してください:
- 業績サマリー(売上・利益・キャッシュフロー)
- 予算との差異分析
- 前年同期比較
- 次四半期の見通し
取締役が関心を持つポイントを中心に、15分程度で説明できる構成でお願いします。
経営会議での問題提起と解決策提案
売上減少や収益悪化などの課題を経営会議で報告する際は、問題提起だけでなく解決の方向性も示すことが大切です。論点整理をするのにAIを活用しましょう。
プロンプト例:
売上が3か月連続で前年同月を下回っている状況について、経営会議で問題提起をします。以下の構成で論点を整理してください:
1. 現状の数値的な事実整理
2. 考えられる原因の仮説
3. 他社・業界動向との比較
4. 短期・中期の改善策の方向性
経営陣が意思決定しやすい形で提案してください。
ステークホルダー別の説明ポイント整理
同じ財務情報でも、相手によって関心のあるポイントが異なります。AIにステークホルダー別の訴求ポイントを整理してもらうのもおすすめです。
プロンプト例:
四半期決算説明を以下の3つの対象別に行います。それぞれが最も関心を持つポイントと説明の重点を教えてください:
1. 株主・投資家向け
2. 主要取引銀行向け
3. 重要な取引先向け
各ステークホルダーの立場から見た注目点を明確にしてください。
プレゼン全体の効果的な構成テンプレート
報告資料全体の流れで迷った時は、AIに基本的なテンプレートを提案してもらうと便利です。
プロンプト例:
経理担当者が経営層に財務報告を行う際の効果的なプレゼン構成を教えてください。「導入→現状→分析→課題→対策→まとめ」の流れで、各セクションに含めるべき要素と、聞き手の関心を引く工夫について提案してください。
資料作成で時短を実現するポイント
AIを活用する際は、現状の数値データと背景情報を整理してから質問すると、より実用的な回答が得られます。また、AIが提案した構成や内容は、あなたの会社の実際の状況や経営方針に合わせてカスタマイズすることを忘れずに。
プレゼン資料の作成時間を大幅に短縮できれば、その分を数字の精査や改善策の検討に充てることができます。AIを上手く活用して、より価値の高い経営報告を目指しましょう。
法務・税務をAIで補助する際は特に出力内容をチェックする
税務処理や法務関連は、経理業務の中でも特に専門性が求められる分野です。AIを活用する際は、他の業務以上に慎重なアプローチが必要になります。
なぜ税務・法務業務でAI利用時は注意が必要なのか
税法や会計基準は頻繁に改正され、AIの学習データが最新情報を反映していない可能性が高いためです。また、法的判断は個別の状況に大きく左右されるため、一般論的なAIの回答では不十分なケースがほとんどです。
さらに、間違った税務処理を行った場合の影響は単なるミスでは済まされません。追徴課税や税務調査の対象となるリスクもあるため、AIの回答は必ず専門家による確認が必要です。
AIを「調査の出発点」として活用する方法
とはいえ、AIを完全に排除する必要はありません。「調査や検討の出発点」として活用すれば、効率的に業務を進められます。
税務処理の選択肢整理では、複雑な会計処理について全体像を把握するのに役立ちます。
プロンプト例:
新規事業の設備投資について、税務上の処理方法にはどのような選択肢がありますか?それぞれのメリット・デメリットと、一般的な適用要件を教えてください。ただし最終判断は税理士に相談する予定です。
内部統制文書の下書き作成も、一般的な枠組みを理解するのに有効です。
プロンプト例:
経費精算プロセスの内部統制文書を作成したいと考えています。一般的な統制手続きの種類と、文書化する際のポイントを教えてください。業界のベストプラクティスがあれば含めてください。
税務調査への備えでAIを活用
税務調査の準備も、AIを「チェックリスト作成」に活用できます。
プロンプト例:
法人税の税務調査で質問されやすい項目と、事前に準備すべき資料のリストを作成してください。製造業・従業員数100名規模の会社を想定して、優先度の高いものから順番に提示してください。
会計基準の理解をサポート
複雑な会計基準を理解する際の「解説役」としてもAIは有用です。
プロンプト例:
リース会計基準(ASU 2016-02)の主なポイントを、実務担当者向けに分かりやすく説明してください。従来の基準との主な変更点と、実務への影響を重点的にお願いします。
契約書の経理的チェックポイント
契約書レビューでも、経理として確認すべき観点を整理するのに役立ちます。
プロンプト例:
業務委託契約書で経理担当者が確認すべき条項と、それぞれの会計処理への影響を教えてください。売上認識、費用計上のタイミング、消費税の取り扱いなどの観点を含めてください。
絶対に守るべき確認プロセス
AIを法務・税務分野で活用する際は、以下のプロセスを必ず守ってください:
AIの回答は参考程度に留めることを徹底し、重要な判断については必ず税理士や弁護士などの専門家に最終確認を取ります。
法令や基準の最新情報は公式サイトで確認し、AIが提示した情報が現行法に基づいているかをチェックします。
会社の具体的な状況についてはAIではなく専門家に相談し、一般論では判断できない個別事案は必ずプロの意見を仰ぎます。
AIと専門家の使い分け
AIは「予備知識の収集」「論点の整理」「チェックリストの作成」に活用し、専門家には「最終判断」「リスク評価」「具体的な対応策」を相談する—この使い分けを明確にすることで、効率的かつ安全に業務を進められます。
法務・税務分野でのAI活用は「時間短縮」と「学習効率向上」がメインの目的です。最終的な責任と判断は必ず人間が担うという原則を忘れずに、上手にAIを活用していきましょう。
まとめ:AI時代の経理プロフェッショナルとして未来を切り拓く
生成AIは経理業務に革命的な変化をもたらし、仕事の質を大幅に向上させる機会を提供しています。
これまで経理担当者の時間の大部分を占めていたデータ入力、計算処理、定型文書作成、繰り返し業務がAIによって効率化されることで、財務データの深い分析、経営陣への戦略的提言、ステークホルダーとの建設的なコミュニケーション、業務プロセスの改善提案といった、より価値の高い業務に集中できるようになります。
AI時代の経理担当者には、AIが提供する分析結果を適切に解釈し活用する能力と、安全にツールを使いこなすデジタルリテラシーが求められます。同時に、AIがどれほど発達しても、「経営陣との信頼関係構築」「複雑な状況での最終判断」「会社の倫理的な財務運営への貢献」といった経理の核心的価値は、人間だからこそ発揮できる領域であり続けます。
まずは本記事で紹介した基本的な活用方法から始めて、継続的に新しいスキルを習得していくことが重要です。生成AIの登場は、経理担当者が自分自身の価値と可能性を再発見する絶好の機会です。「AIで仕事を進化させる」という成長マインドセットで、新しい時代の経理プロフェッショナルとしての道を切り拓いていきましょう。